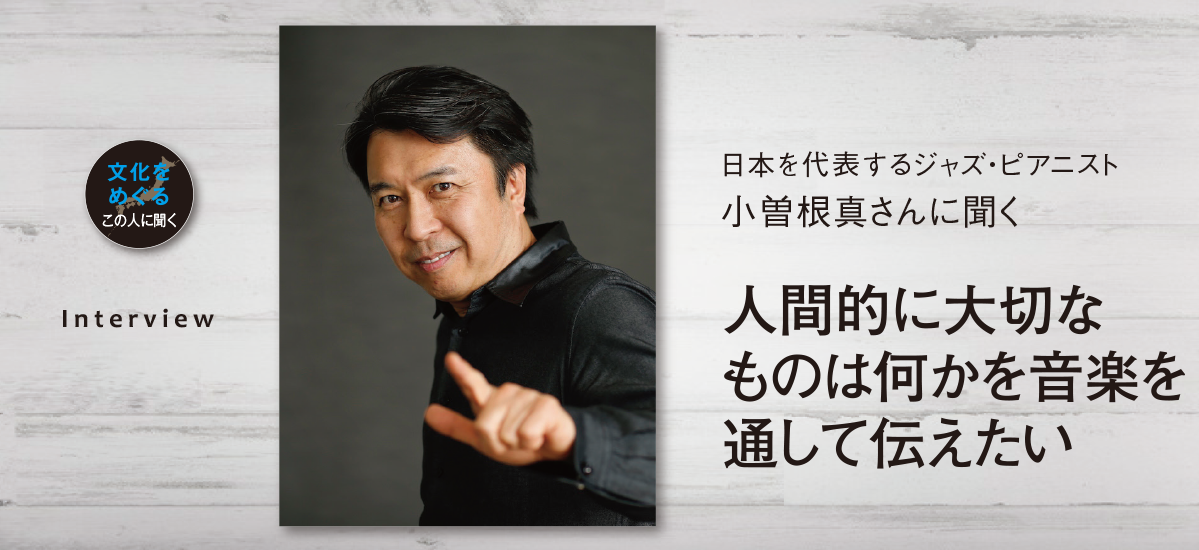

アルバムデビューから30年を超え、名実ともに日本を代表するジャズ・ピアニストとして活躍する小曽根真さん。80年代初めに学んだ米ボストンのバークリー音楽大学時代の学友たちが、現在のジャズ界で重要なポジションを占めており、ブランフォード・マルサリスを始めとする著名なミュージシャンとの共演関係を続ける小曽根さんは、すでに世界標準となっています。
現在では、その活動はジャズに留まらずクラシック界にまで拡大し、国内外でのオーケストラ・プロジェクトでも評価を高めています。
その小曽根さんに日本と海外との音楽観の違い、日本への思いなどをお尋ねしました。
小曽根真(おぞね・まこと)
1983年にバークリー音楽大学ジャズ作・編曲科を首席で卒業。同年、米CBSと日本人初のレコード専属契約を結び世界デビュー。 以来、ソロ・ライブをはじめゲイリー・バートン、ブランフォード・マルサリス、パキート・デリベラなど世界的なトップ・プレイヤーとの共演や、自身のビッグ・バンド「No Name Horses」を率いてのツアーなど、ジャズの最前線で活躍。2011年より国立音楽大学(演奏学科ジャズ専修)教授に就任し、2015年には「Jazz Festival at Conservatory 2015」を立ち上げるなど、次世代のジャズ演奏家の指導、育成にもあたる。 近年はクラシックにも本格的に取り組み、国内外の主要オーケストラと共演を重ね、高い評価を得ている。2018年 紫綬褒章受賞。

音楽を言葉として捉える
欧米と日本の音楽に対する考え方の違いは、欧米では音楽=言葉だと捉える点です。言葉があって、そこから音楽が生まれるという感覚を持っているから、言葉に対する感覚も音楽に近い。例えばアメリカ映画でニューヨーク生まれの俳優がテキサス人を演じる時に、完璧な南部訛りの言葉を話します。それが可能なのは、ぼくは、彼らが、言葉を音楽として捉えているからだと思っています。音楽を聴くように言葉をきいているのでしょうね。だからアメリカの俳優が現地の言葉を覚えるのが早いわけです。
日本の場合は、ドラマや舞台を見ていると、関西人のぼくが違和感を覚えるイントネーションで関西弁を話す役者さんがいますが、この感覚の違いかと思っています。
演奏者の個性を活かす
例えばカウント・ベイシー楽団のメンバー達は「自分ならこう演奏する」という意識で音を出しています。中には他のメンバーよりも飛び出す感じの人もいるけれど、それが全体でまとまった時に、幅の広いサウンドになって楽しい。これがジャズというアメリカが生んだ音楽のダイナミックさだと思っています。
対して日本人のビッグ・バンドの場合は、ピッチも吹き方も他の演奏者に合わせるから、その点では完璧だけれど、でも全然ジャズの響きになっておらず、ジャズっぽい演奏になってしまっているケースがあります。そこには日本人の生真面目な気質があって、それはそれで素晴らしい事ですが、これは音楽教育の方法にも原因があるでしょうね。アメリカの教師はまず生徒に「グッド!」と言ってから始まる。日本の教え方は、まず間違いを指摘することから始まるから、どうしても生徒が硬くなってしまいます。
褒める事があまり上手くないというのが日本人の弱い部分ではないでしょうか。良いリーダーの下ではパワフルなチームとして動くことができます。日本人が欧米のミュージシャンのように自分の個性を信じる意識を持った時の瞬発力はたいへん強いと思いますので、それを生かすのが大切です。

自分の持っているものを提供する
クラシックが看板だった国立音楽大学が、2011年に演奏学科「ジャズ専修」を立ち上げて、ぼくは教授に就きました。大人数だとどうしても取り残される学生が出てしまうので、1学年を最大18人に決めて、目が行き届くようにしています。指導者の姿勢としては、「教える」ではなく、「自分の持っているものを提供する」というアメリカ式の方が好きですね。アンサンブルの場合、他の人の音をいかにちゃんと聴いているか、が何よりも重要。自分の主張をするなら、他の人の演奏を理解することが求められます。小手先のテクニックや上手にごまかした演奏は厳しく指摘します。なぜなら音楽に真正面から取り組むことが大切だからです。自分の入魂の音を出せば音楽に意味が生まれ、お客さんにも伝わるのです。

音楽を通じて伝えたいこと
国立音楽大学の方法を他大の学生たちにも広めたいと思い、2015年に国立を含む4校が「ジャズ・フェスティバル・アット・コンサバトリー」(JFC)を合同で立ち上げました。ジャズを専門的に学ぶことができる音楽大学の一般的な認知と、学生の意欲を高めることが目的です。2016年の《東京JAZZ》では選抜メンバーによるJFCオールスター・ビッグ・バンドと、アメリカの名門、ジュリアード音楽院の精鋭アンサンブルが共演。2017年には米イーストマン音楽院のアンサンブルがJFCに参加してくれて、JFC発足から4年目にあたる2016年の《東京JAZZ》ではプロとして活躍するJFC出身者も参加したオールスター・ビッグ・バンドを編成しました。
JFCではフランスやロシアともネットワークを作ろうと思っています。いずれは全国の音大にも拡大したいですね。
人間的に大切なものは何かを、音楽を通して伝えたい。ぼくの生き方を見ていただき、それが学生たちの糧になればいいと思います。恩師であるチック・コリアやゲイリー・バートンから学んだことが、まさにそれなのです。

私が大切にしている日本
和食
下ごしらえされて、食材の本質的な味を引き立たせる調理法の和食は、ずっと好きです。白米はもちろん好きですが、自宅では専用の炊飯器で炊いた酵素玄米を食べています。きっかけは身体のことを考えたから。玄米と小豆をいっしょに炊いて71度で保温すると、そこからどんどん酵素が生まれて6日間くらい経つと更に美味しく食べられます。年齢と共に味覚で感じるものと、身体で感じるものと、食事の喜びが二つになってきました。
方言
尊敬する井上ひさしさんの戯曲『組曲虐殺』の音楽を担当した時に、北海道弁の魅力を知りました。コンサートで地元の神戸に帰った時は関西弁になります。その方が観客との距離が近くなるので。方言の音を練習して各地を訪れると、皆さんが感じていることをぼくも感じられて繋がり合えるのです。メロディやリズムで感情を表現する音楽家の立場で言えば、方言をもっと大切にすることを多くの人たちが意識する必要があると思います。
真面目さ
戦後、日本が急速に復興を遂げたのは、これをやると決めたら一体となってその方向に進む日本人の気質があったからだと思います。音楽では完璧なレコードコピーができる民族だと認識することも大切で、それは島国の日本だからこそ培われてきたDNAによるものです。東日本大震災の時に暴動が起こらなかった日本が海外で驚かれたように、規律の正しさという共通感覚を持つ日本人の生真面目さは、世界に誇れる要素です。
(写真・工 晋平/協力・株式会社ヒラサ・オフィス)










